PCA教材の紹介
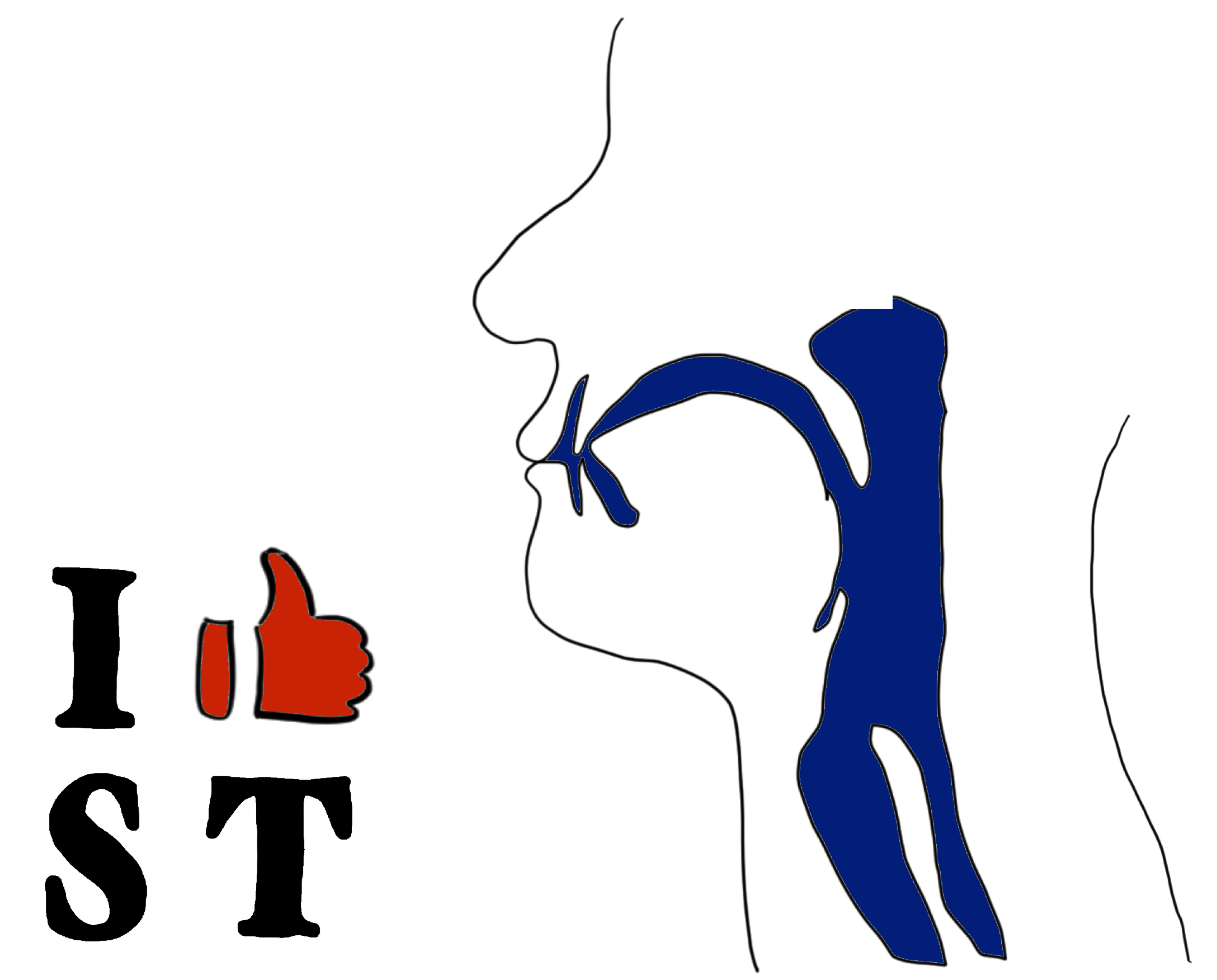
こんにちは、おくららです。
今回はPCA教材を作成したので紹介です。
PCAについて
SFAについては以前に紹介したので、ご存じない方はこちらを読んでもらうのが良いかと思います。PCAの国内の論文は少ないので、今後増えてくる可能性があります。知っておいて損はない方法でしょう。
んで、今回は簡単にできるように絵と質問を組み合わせたものを作成しました。
一般的なものと質問の配置がことなりますが、用紙を印刷し行うことを考えてやりやすさ重視で変更しています。
PCA(質問あり)
絵に対して質問が書かれています
SFAの時には空欄のものも作成しましたが、PCAは他の質問を用いることがないと思いますので、空白の物は作成しておりません。
もしくはSFAの空白のものを利用してもらえば問題ないです。
SFAの紹介と教材紹介の記事はこちらから。
PCAの方法
英語論文ですが詳細に紹介してくれているものがあったので、それをもとに方法を紹介します。
Rhymes: ‘‘What does this rhyme with?’’
First sound: ‘‘What sound does it start with?’’
First sound associate: ‘‘What other word starts with the same sound?’’
Final sound: ‘‘What sound does it end with?’’
Number of syllables: ‘‘How many beats does the word have?’’
Carol Leonard,Elizabeth Rochon,Laura Laird.Treating naming impairments in aphasia: Findings from a phonological components analysis treatment.Aphasiology.2008
ステップ1
絵に対して呼称を行う
ここでは、誤っていても修正することはしない
ステップ2
絵の周囲にある質問に答えてもらう
正しい内容であればボックスの中に書き込み、誤っていれば選択肢などを提示する
ステップ3
呼称を行う(上記のプリントの場合には質問を隠すように用紙を折る)
質問の内容からヒントを与える
このような手順で行っていきます。
※rhymeの翻訳がわからないので、そこは自己責任でお願いします。
SFAと同様に、他のカードで用いる場合には、ホワイトボードを利用すると良いと思います
まとめ
今回は失語症教材のPCAを紹介でした。
賛否両論だと思いますが、私はSFAやPCAの手順を遵守しなくとも良いと思っています。
もちろん、しっかりと評価し適応に関して判断し手順に沿って行うことは大切ですが、症状に合わせて上手に誘導するのは言語聴覚士の腕の見せ所だと思うからです。
作成した教材は臨床での現状に合わせて上手に使ってもらえればうれしいです。
これからも色々な訓練課題を作成していきます。
皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。
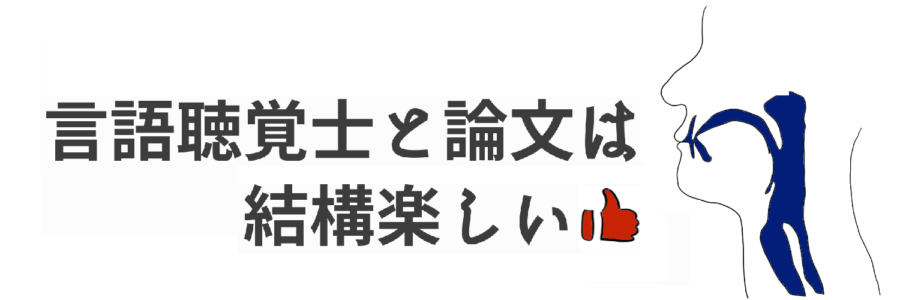





コメント