全体構造法について考える
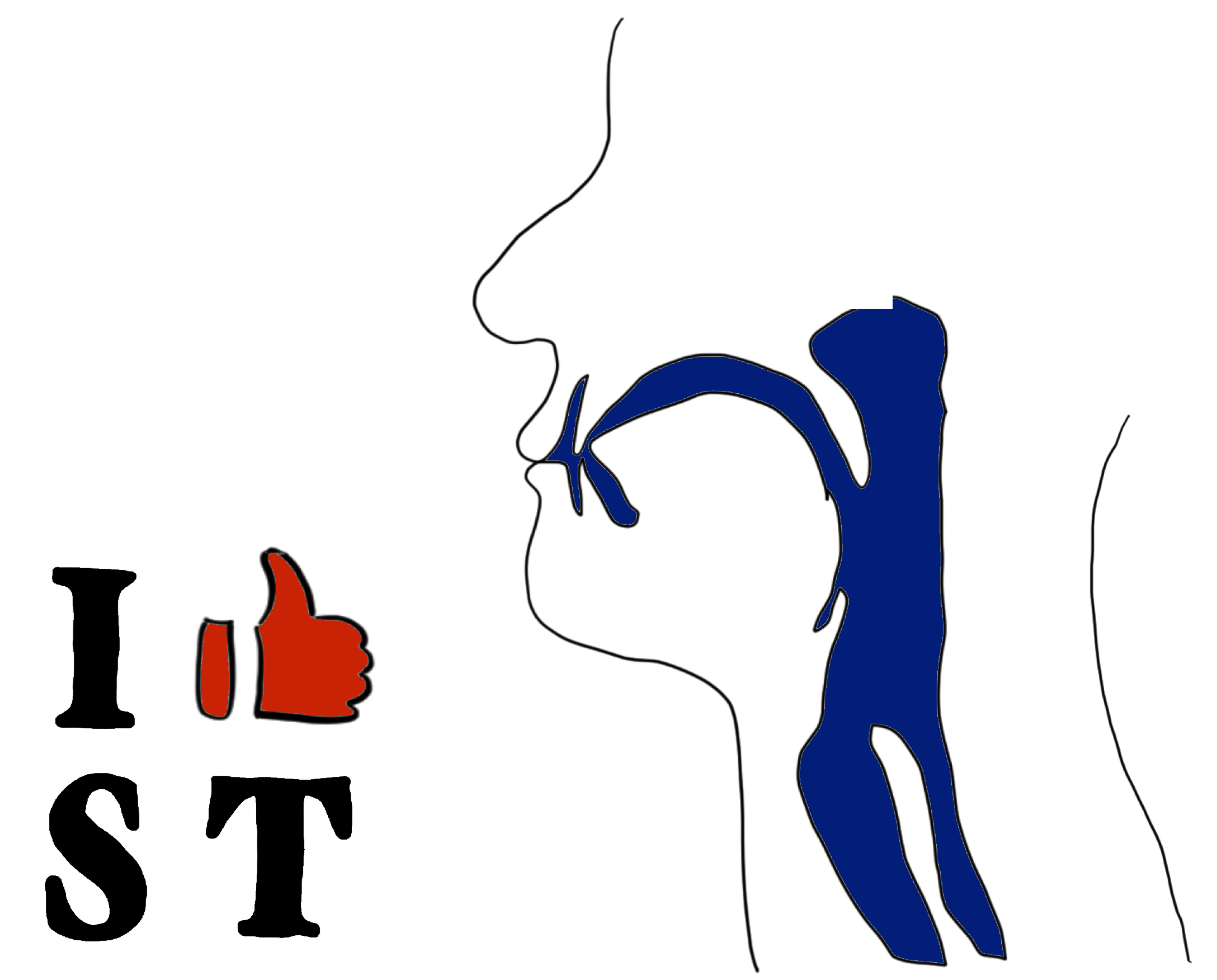
失語症のリハビリテーションには色々な方法があると思いますが、本日は全体構造法(JIST)です。道関先生の論文がありましたので、それを参考に少し意見を書いていこうと思います。
JISTってどんなものなの?
現在様々な方法で失語症のリハビリテーションが行われていると思います。刺激法や遮断除去法、認知神経心理学的モデルを用いてを用いたアプローチなど様々です。その中の一つに全体構造法があります。
本日は全体構造法(JIST)について考えていきたいと思います。
ほーーーーーーーーーんとに一部のみの紹介なので詳細を知りたい方には物足りないと思います。
知りたい人は初級講習や書籍を購入することをお勧めします。ちなみに、僕は興味があるのでJISTの初級講習を数回受講し、学会にも参加しました。
結論から書くと『不連続刺激は明日からでも臨床で活かせる』です。
学校では習わなかった用語が多いので論文だけで理解するのは難しいです。
ただ、考え方に関してはすごく参考になると思うので論文などで読む価値は十分あります。
まずは、JISTについて論文から引用していきます。
人間を知覚の全体構造体としてとらえ、その全体構造体人間の意識活動である言語活動の発展という本筋から臨床を考えていく体系が全体構造法である。本法はテクニックではないので、開発した各手段は、本法の基本認識である「知覚構造化を進める」をふまえて編成されなければ有効な効果は得られない。
道関 京子.〈失語症のセラピィ〉全体構造法とは何か.コミュニケーション障害学.23巻1号.2006
(略)
脳は新しい体験、新しい知覚要素を既存の神経ネットワークに組み込み、全体として新たなネットワーク、新たな意味を構成する。
(略)
知覚すなわち構造化とは受け身な活動ではなく、自ら信号を感じ気づく、能動的な脳の活動である。
恥ずかしながら僕には少し難しいですが、能動的に気付いてもらい、ことばのネットワークを編成していくというイメージですかね?間違ってたらコメントで指摘してください。
知覚が受け身ではなく、能動的にという点は全体構造法に限らず、どのように気付いてもらうかは重要ですのでとても参考になりますね。
具体的な手技
話しことばの構造化を進めるための具体的手段として、①となえうた、②身体リズム運動、③不連続刺激を用いる。
道関 京子.〈失語症のセラピィ〉全体構造法とは何か.コミュニケーション障害学.23巻1号.2006
(略)
これら本法の手段は、言語障害者の一人一人の現段階の知覚目的に合わせて編成していくものなので、どれもマニュアル化することはできない。
各手段の説明に関して論文に記載されています。
手段に関してマニュアル化することが出来ないと記載されていますが、現在もマニュアル化はされていないです。個別性を重要にしているのでマニュアル化できないということなのだと思います。
他のアプローチでもそうだと思いますが、完全に障害と手段があっているのは少ないと思います。症状から症状の根本となる原因を考えて介入する必要があると思います。
各種マニュアルに記載されているのは手段であり、期待できる効果だと思うのでうまく組み合わせるのが大切ですよね。
おくららが臨床で思うこと…
この論文では手技に関してはほとんど記述されていないのでさすがにこれだけ読んで全体構造法を実践できるわけではないです。もちろん著者の道関先生もそのような目的で執筆なさっていないと思います。
ただ、知覚のことを知るには参考になると思います。
特に不連続刺激という考え方は参考になると思います。
ざっくり言うと、同種の刺激ではなくて、異種の刺激を与えて気づきを促すってことです。
15度の水と20度の水飲んでも何も差を感じないと思うけど、50度の水やったら温度の差に気づくでしょ?自然と温度の際に意識が向くでしょ?そういう感じのことです。
先日から気づきのことを書いていますが、そういうことを言いたかったんです。
JISTを勉強して本当に意識するようになりました。
どんな刺激で、どんなタイミングで、どんな方向から刺激(課題や声かけやポインティング)を与えるべきなのかは本当によく考えます。
JISTに関係なくすべての課題で考えなくてはいけない視点だと思うので明日からの臨床で活かしてもいたいと思います。
JISTの細かい実践方法は書籍にはかなり詳細に記載されているので、初級講習や学会、書籍を参考にしながら行うことをオススメします。特に書籍にはタイプごとの各手技や実践方法などに関して詳細に書かれているので興味のある方は購入してはいかがでしょうか。
これからも色々な視点から考えていきたいですね。
皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。
引用:道関 京子.〈失語症のセラピィ〉全体構造法とは何か.コミュニケーション障害学.23巻1号.2006
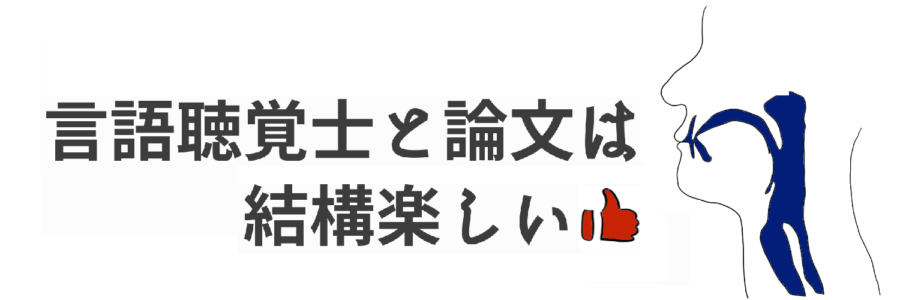


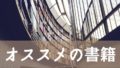
コメント