とりあえずこれは読んでほしい5冊
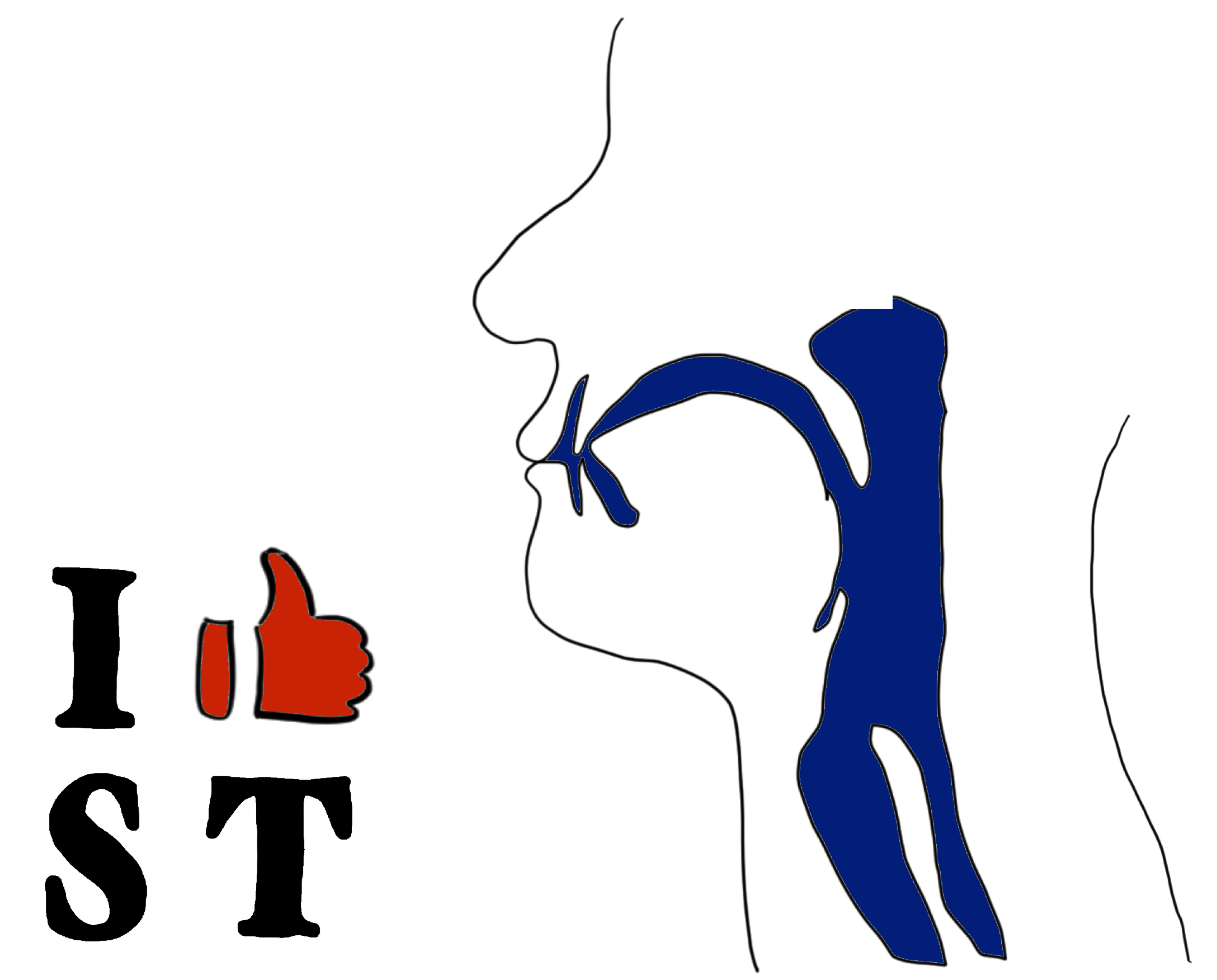
構音障害分野の勉強をする際に是非読んでほしい本を紹介します。
少しマニアックな本ですが臨床にすぐに役立つ本ばかりなのでぜひ手に取ってみてください。
勉強会や講習会で講師をしていると、どんな風に勉強していますか?と聞かれることも多く、構音障害に関しておすすめの本について聞かれることがあります。
今回は構音障害を勉強するときによむべき本について紹介していきます。
あえて、標準化されているテキストは紹介しません。
だって少しマニアックなぐらいが面白いからです。
神経原性発声発語障害 dysarthria
まずは、『神経原性発声発語障害 dysarthria 』です。本当は授業のテキストにしてほしいぐらいわかりやすいです。学校の授業でもたくさん引用させていただいています。著者の苅安先生は運動障害性構音障害の第一人者ですので、大変参考になります。苅安先生の臨床知と研究知がギュっと凝縮されている一冊です。
タイプ分類に関しても特徴がタイプごとに表にまとめられていてわかりやすいです。特に学生さんは国家試験にタイプと特徴のマッチング問題が頻発なので抑える必要があります。
訓練法に関しても、訓練の立て方から具体的な方法まで詳細に記載されています。刺激―反応―対応にわけて表にしてあるので臨床の具体的な関わり方の参考になると思います。そこで何を観察しているのかを整理することで臨床での応用力が養えると思います。
個人的には補足資料の音響分析の部分は専門書を読む前に読んでおくと良いと思います。短いですが必要な部分だけ書いてくれています。苅安先生は音響分析の講演をよくなさっているので、本当にわかりやすくまとめてくれています。
名著なので是非購入してみてください。
運動性構音障害 (アドバンスシリーズ・コミュニケーション障害の臨床)
次は、『運動性構音障害』です。10年ぐらい前に購入して今も大切にしている本です。いろいろな先生が書いてくださっていますが、椎名先生と長谷川先生の章はよく参考にします。よく質問される「先生はどんな本で手技を学びましたか?」の答えとなる本です。
タイプのことなども書かれていますが、具体的な徒手的な介入に関して書かれている部分はいまだに参考にします。図も多く、大変わかりやすくまとめられております。
顔面や舌のリハビリを決められた運動を決められた回数だけどの患者さんにも行っていた頃にこの本をきっかけにして変わることが出来ました。反応を評価して訓練に活かすことの基礎を教えてくれた本です。
呼吸や発声に関しても徒手的な介入方法に関して書かれています。当時の僕はブローイングだけやってればいいわけではないと反省しました。言語聴覚士の苦手な呼吸のリハビリのヒントになると思います。
2002年の本ですので、もちろん情報の選定は必要ですが、今読んでも参考になる本だと思います。
不朽の名作なので是非購入してみてください。
脳卒中の治療・実践神経リハビリテーション
続いて『脳卒中の治療・実践神経リハビリテーション』です。ボバースアプローチに関係する先生方が書いている本です。これも椎名先生と長谷川先生の章は非常に参考になります。ボバースの研修会を受講する前に読んでおくと良い本だと思います。
顔面や舌の介入の方法、呼吸のリハビリについて大変わかりやすくまとめてあります。『運動性構音障害』と重複する部分はありますが、内容がアップグレードされているという具合です。
手技に関してももちろんですが、考え方の視点を学ぶことが出来たと思います。知覚探索のことやリハビリの原則みたいなことも書かれている部分があるので臨床で大切にしている部分です。
2010年の本ですので、やはり情報の選定は必要ですが、いまだに勉強させられる本だと思います。
原点となる本だと思うので是非読んでみてください。
ビジュアル音声学
『ビジュアル音声学』ですが、めちゃくちゃわかりやすい音声学の本です。入門から中級ぐらいだとこれでかなり理解が深めれると思います。
調音音声学ではMRI、超音波、EPGなどの様々な視点から調音運動を解説し、音響音声学でも必要最低限の数式で説明してくれます。知覚音声学でも聞こえ方について様々な視点から紹介してくれています。
音声で症状を評価することの多い言語聴覚士が把握しておかないといけない音声学の知識はほとんど書かれているのではないでしょうか。
学生と若手言語聴覚士はもちろん中堅言語聴覚士の方で音声学の再学習を考えている方はおすすめです。
新ことばの科学入門
ことばに関して基礎的な内容が丁寧に書かれている本です。中でもことばの音響学の部分はかなり参考になりました。母音と子音の音響学についてまとめられており、みんなが苦手な音響学が分かりやすくまとまっていると思います。
発声に関してもわかりやすく書かれています。言語聴覚士として、発声はよく介入すると思いますが、この知識があれば、ある程度反応から評価が出来て介入につなげられると思います。もちろん詳細には研究を調べる必要がありますが、基礎となる部分は網羅されているといってよいです。
音響学の専門書を買う前にビジュアル音声学か新ことばの科学入門を購入することをお勧めします。
さいごに…
古い本は参考にならないはあり得ません。
もちろん日進月歩の業界なので古い情報であることは確かです。
ただ、新しい論文だからって絶対正しいという保証はないです。
情報を選定するのは自分であって視点が増えることは間違いないです。
情報がないのに何が正しいかなんてわかりっこないんです。
知識を蓄えて、臨床で向き合うことで新しい発見があるのだから、たくさん読んでたくさん臨床で挑戦していくことが臨床家として大切な姿勢だと思います。
是非皆さんの臨床の助けになればよいなと思います。
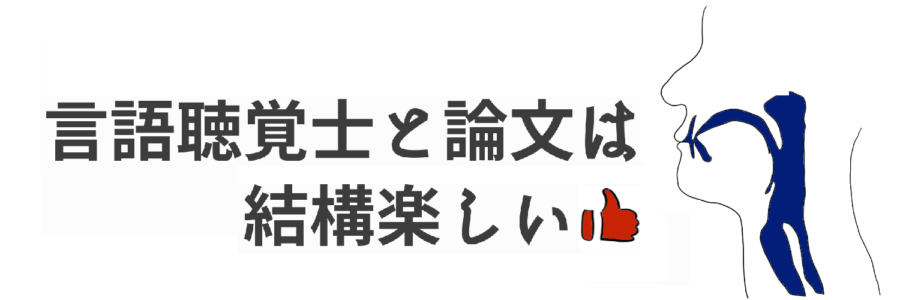
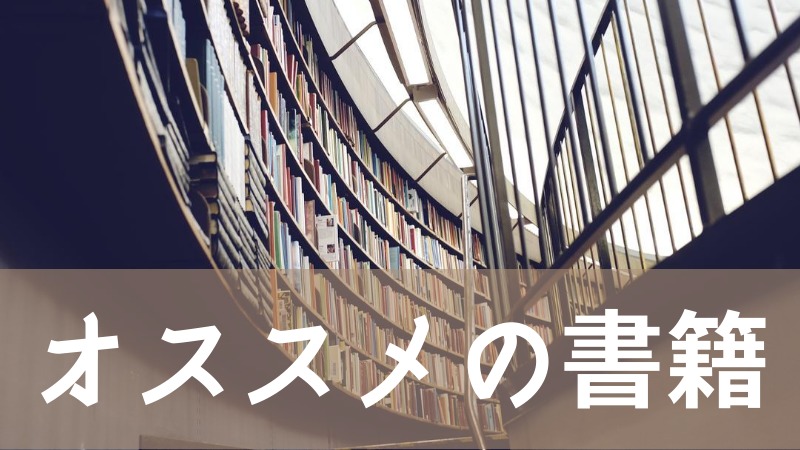


コメント