食物通過について考える
口峡の通過について筋紡錘の視点から
ある先生は「本当に最終的な食塊形成は軟口蓋と奥舌でされるんやで」と言っていました。
おそらく臨床知の話だと思いますが、最後は奥舌や軟口蓋が大切であることはすごく共感します。
自身の経験としても軟口蓋挙上や奥舌挙上が不十分だったり早期咽頭流入の際に嚥下異常音が生じることもあるので口腔期~咽頭期の重要性は感じることが多いです。
今回は咽頭期の嚥下メカニズムというよりもその少し前のメカニズムについて論文を紹介します。
舌内の筋紡錘の分布を調べたところ、同部(舌根の高さ)の横舌筋とこれに直行するオトガイ舌筋の筋線維にのみ集中して分布していることがわかった。
三枝 英人.構音器官の運動性から考える―その評価法と新しいDysarthria治療の可能性―.音声言語医学.48巻3号.2007
口蓋帆挙筋以外の筋、とくに口蓋帆張筋と口蓋舌筋には大型の筋紡錘が稠密に分布し、口蓋帆挙筋には小型の筋紡錘がわずかにしか分布されていない。
舘村 卓.食物物性および一口量の嚥下機能に対する影響 : 口蓋帆咽頭閉鎖機能に焦点を当てて.日本味と匂学会誌.17巻2号.2010
口蓋帆が挙上して口峡を食物が通過し始めることで口蓋舌筋の活動のtriggerが生じ、食物の物性や量にかかわらず、口峡開大後から個人ごとに固有の時間差で奥舌が挙上する。(略)口蓋帆が挙上する際に前口蓋弓に収容されている口蓋舌筋は一気に伸展される。
舘村 卓.食物物性および一口量の嚥下機能に対する影響 : 口蓋帆咽頭閉鎖機能に焦点を当てて.日本味と匂学会誌.17巻2号.2010
今まで口蓋舌筋や口蓋帆挙筋、口蓋帆挙筋の筋紡錘について考えたことがないので大変参考になりました。口蓋舌筋が他動的に筋長が変化し活動するのは興味深いですね。
めちゃくちゃ口蓋舌筋が奥舌で咽頭に送り込みの話で挙がる印象はありませんが、筋紡錘が多いといわれると一気にイメージできるようになりました。
機能も確か『舌根を挙上させ口腔と咽頭を閉鎖させる』とかだったと思います(自信ないので調べてみてください)。筋の配置を考えても上方に挙上させるのは間違いないですもんね。
口蓋帆挙筋にではなく、口蓋帆張筋に多いのも面白いです。
たしかに、軟口蓋を平坦にしておく必要のある口蓋帆張筋ですが、軟口蓋のが下垂してしまわないように筋紡錘で制御しているのだと考えるとすごく理にかなっています。
※ここからは僕の疑問点と考察です
ここで疑問なのが、
発声の時にはどうなんだろうか?
もちろん発声の時にも軟口蓋の挙上はありますよね。
その時には働かないのだろうかと思いませんか?
僕は思って考えてみたんですが、発声発語と嚥下運動の制御系の違いではないかと思います。
嚥下運動はフィードバック機構の働きが重要であると考えています。
もちろん、随意的に上位からの制御もありますが、末梢からの刺激に対してオートマチックに働くフィードバック制御が重要であると考えます。
一方、発声発語は運動を行う前にすでに決められた運動を行うフィードフォワード制御が重要であると考えます(お師匠さんはよくセントラルプログラムという言葉を使ています)。
発声発語の際に軟口蓋が挙上することをプログラムすると同時に口蓋舌筋の伸張に対しての抑制をしているのかもしれません。
これだったら面白いなと思ってます。
ただ、単純に発声発語と嚥下運動の口蓋帆の挙上に差がある可能性もありますよね。
そういった論文あったら教えてください。僕も調べてみます。
これからも色々な視点から考えていきたいですね。
皆さんも気づいたことがあればコメントやコンタクトで意見ください。
引用:三枝 英人.構音器官の運動性から考える―その評価法と新しいDysarthria治療の可能性―.音声言語医学.48巻3号.2007
舘村 卓.食物物性および一口量の嚥下機能に対する影響 : 口蓋帆咽頭閉鎖機能に焦点を当てて.日本味と匂学会誌.17巻2号.2010
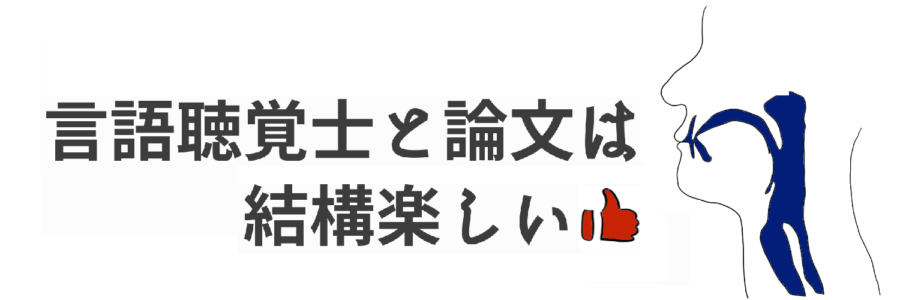


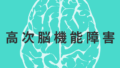
コメント